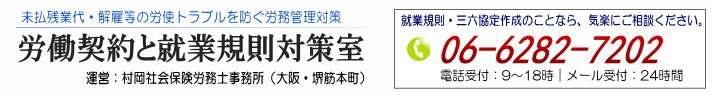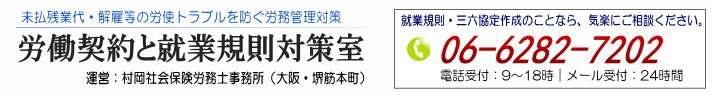これまで、労働契約に関するルールは民法や労働基準法、それ以外では
裁判所の判断等にゆだねられてました。最近では、終身雇用制度の崩壊に
より、多種多様な労働形態が増え、労働条件は個々に決定・変更されること
が多くなり、労使トラブルも個別化してきました。
労働契約法はこれら労使トラブルを未然に防ぐため、判例などを基本に労働
契約に関する民事的なルールをまとめたものです
労働契約法の規定の多くは、判例を法理を明文化したもので、労働基準法
と異なり罰則を伴いません。
労使関係のトラブルを未然に防ぐために労使当事者が労働契約に関し、
注意しなければいけない一定の基準の役割があります。
◆労働契約法の目的(労働契約法第1条)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意
により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する
基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑
に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働
関係の安定に資することを目的とする。
◆労働契約法は民法の特別法
・労働契約も契約である(民法の原則:私的自治の原則、契約自由)
・労働契約に関する基本的事項を定めている
・労働者保護を図る(民法の原則を修正する)
◆罰則がない
労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律の性格上、義務の履行を
強制するために罰則が設けられている。
労働契約法は民事法のため当事者間の自主的な決定にゆだねられるため
罰則をもって強制することはなじまないため、罰則がない。
最終的な判断は裁判所などが担当することになります。
◆用語の定義(労働契約法第2条)
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払
われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を
支払う者をいう。
◆労働者・・・労働基準法第9条 労働者と同じ
形式が請負、委任契約であっても契約当事者間に使用従属関係が認めら
れ、労働者としての実態がある場合には請負人、受任者も労働者に該当
します。
◆使用者
事業主を指します。労働基準法第10条の使用者の定義より範囲が狭い
事業の経営担当者、労働者に関する事項について事業主のために行為
する者は含まれない
|